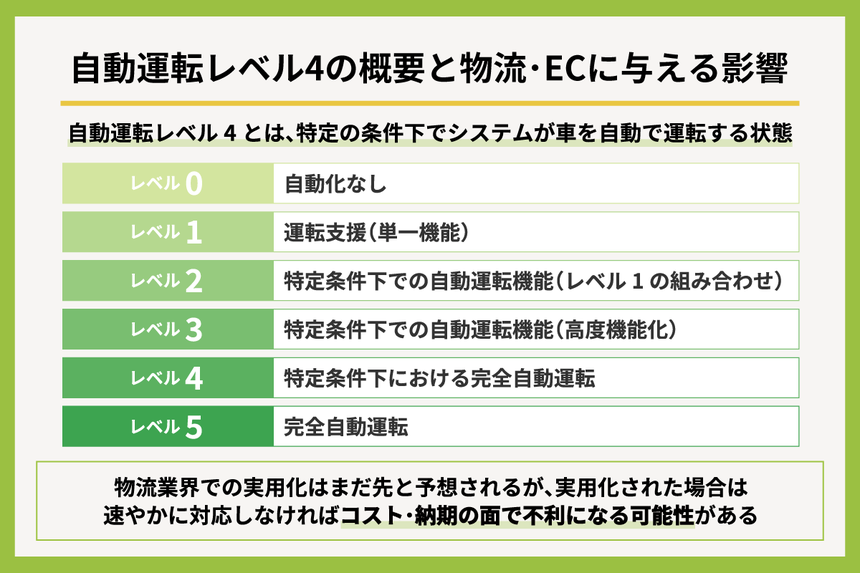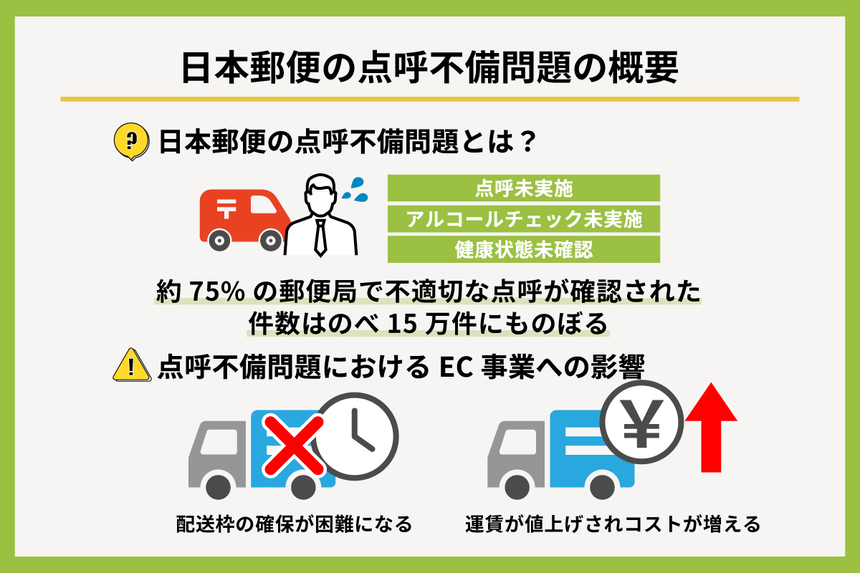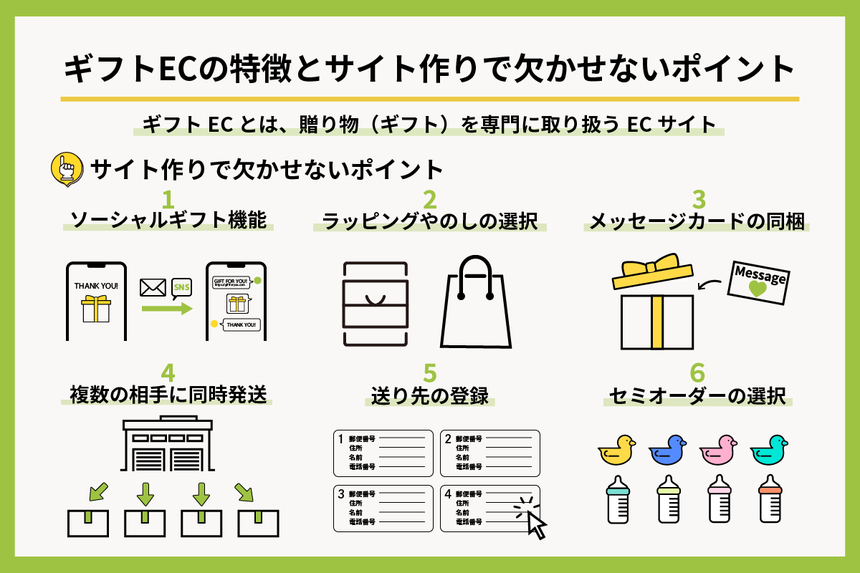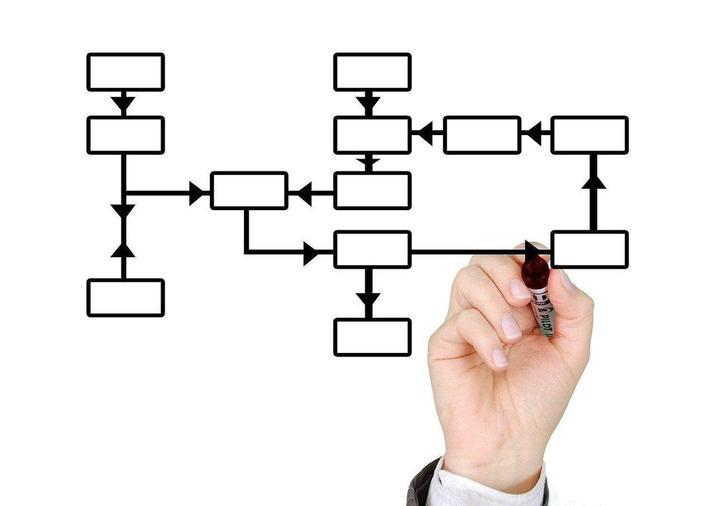
- 目次
物流委託(物流アウトソーシング)とは

物流委託とは、自社で行っている物流機能のすべてもしくはその一部を切り離し、物流のプロフェッショナルである外部の企業へ業務委託することです。
業務を委託することで、人的リソースや在庫の保管・管理といった自社では対応しきれない悩みを解決することができ、物流に関連するノウハウがない企業も高い水準の物流サービスを提供できるのが特徴です。
自社物流と物流委託の違い
物流業務を自社でまかなう場合と物流委託する場合を比較すると、主にリソース面で次のような違いがあります。
| 物流の種類 | 自社における物流の範囲 | 大きな違い |
| 自社物流 | 物流業務の全般 | 物流業務におけるリソース負担が大きい |
|---|---|---|
| 物流委託 | なし~物流業務の一部のみ(物流全般もしくは一部を専門業者が担当) | 委託した分、リソースの悩みが軽減される |
自社の物流業務を物流サービスを専門とする企業に業務委託する形態を「3PL」と言います。自社で担っていた物流業務の全般もしくは一部を委託することで、これまで物流にかかっていたリソースが軽減されるため、物流以外の業務に集中できるようになります。
物流委託を利用する企業の割合
物流委託がどういうものか理解できたものの、どれくらいの企業が実際に活用しているのかが気になるところだと思います。
中小企業庁の調べ(※2)によると、31.3%の企業が実際に物流委託を活用し、自社の物流業務を強化している現状があるため、物流に課題を抱えているのであれば、物流委託を利用するのもひとつの方法と言えるでしょう。
特に、卸売業では物流委託を活用・強化する企業が多く、業種別では食品・雑貨や機械の物流委託率が40%を超えています。また、製造業でも電気機械で40.0%、飲料・食料も33.3%となっており、活用する企業の割合が高い傾向です。
※2 出典:経済産業省 中部経済産業局「物流アウトソーシングマニュアル~持続可能な物流効率化を目指して~」
物流委託が可能な業務内容・作業範囲

ここまで、物流委託の概要を説明しました。その中で、物流委託について興味がわいてきた担当者もおられると思います。そこでこの章では、物流においてどのような業務や作業を委託できるのかを解説します。
近年増加傾向にある、注文データの処理からカスタマーサポートまでを一環して行う サービス「フルフィルメント」についても触れていますので 、ぜひ参考になさってください。
入荷(入庫・検品)
物流会社にとって、とても重要な商品の入庫と検品を行います。入庫では、指定商品の受け取り、検数(数量の確認)、格納まで対応するケースが多くあります 。また、検品では、汚れや破損の確認など を 行い、商品の管理をするのが特徴です。
保管
物流委託企業の庫内で、入荷した商品の保管・資材管理を行います。
出荷(ピッキング・梱包)
注文に応じて棚から出荷する商品をピッキングし、豊富な梱包材の中から商品に合った段ボール、エアー緩衝材などで梱包して積み込み、伝票発行作業までを代行します。
配送
注文通りにセットされた荷物を、お客様や店舗などに配送します。
返品(顧客返品処理・良品加工・メーカー返品)
商品にもよりますが、商品の受け取り拒否やお客様の不在、不良品などによって返品された場合には、再入庫作業などの対応を行います。メーカーへ返品するためのピッキング作業や梱包、出荷作業も行っているため 、返品処理を任せることも可能です。
フルフィルメント
フルフィルメントとは、顧客による商品の申し込みから手元に届くまでに必要な業務全般を指す言葉です。入出荷や在庫管理、ピッキング・梱包などの範囲を委託できる3PLよりも広い業務範囲をカバーできるという特徴があります。
物流委託を導入する4つのメリット

前項までで 簡単に、物流においてどのような業務や作業を委託できるのかを説明しました。これらを踏まえ、物流委託を導入するメリットを4つ紹介します。
【費用】コスト削減と明確化を実現できる
まず1つ目が、自社で物流を担うよりもコスト削減できる可能性があり、どのような物流にコストがかかっているのかを明確化できるという点です。
経済産業省の資料によると 、物流を行う企業の多くが物流委託することでコストカットできることをメリットとして挙げています。
すべてを自社でやろうとすると、忙しくなりそうな時期は、先を見据えて、人の配置や保管場所を増やす必要がありますが、もし売り上げが伸びなかったら、人件費や保管費分は損失となりますよね。
しかし、物量によって価格が変動するタイプの物流委託を利用していれば、物量に合わせた費用だけがかかるので、機会損失を防ぐことができます。また、物流委託することで、物流のプロがコスト管理もしっかりと行ってくれます。そのため、何にどれだけかかっているのかというのも明確に把握できるようになり、物流コストをより細かく管理できるようになります。
※3 経済産業省 中部経済産業局「物流アウトソーシングマニュアル~持続可能な物流効率化を目指して~」
【工数】業務効率化ができる
2つ目は、物流における業務負担が減ることで、その他の業務効率を高められるという点です。
自社だけだとキャパシティが限られます。実際、前出のデータでも荷主企業の半数以上が物流課題を抱えている現状が見られますが、物流委託をすれば、物流以外のコア業務に集中できるようになります。
営業や商品開発などに人や時間を割くことができるので、さらに売り上げを伸ばすこともできるでしょう。
【品質】物流品質の向上が期待できる
3つ目が、物流のプロフェッショナルに任せることで、自社にはないノウハウを活かして物流品質を高めることができるという点です。
閑散期・繁忙期に関わらず、丁寧かつスピーディーに対応できるようになります。物流品質は、顧客満足度にも直結する部分なので、物流委託することで企業評価が高まり、売り上げアップも見込める可能性があります。
【人材】人材確保や育成・管理のリソースを軽減できる
4つ目は、人材にかかる一連のフローを軽減できる点です。
自社でまかなう場合、業務に応じた必要人数を把握し、欠員が出ると補充しなければなりません。新入社員やパート・アルバイトといった新しい人材が入ると育成が必要になり、人が増えた分管理も大変になります。しかし、物流委託してしまえば、プロが物流現場でのスタッフ育成や管理を担当してくれるため、そこにかかっていたリソースを軽減できるでしょう。
物流委託を導入する際に考えられる2つのデメリット

メリットについてみてきましたが、その一方で、デメリットもあります。
【ノウハウ】物流におけるノウハウが蓄積しづらい
1つ目が、自社において物流のノウハウが蓄積しづらいという点です。専門的な物流サービスを受けられるのは大きなメリットですが、業務委託した部分は、ノウハウが得られにくくなるという懸念もあります。
物流において、今後もアウトソーシングを上手く活用していくのであれば大きな問題ではありませんが、「ゆくゆくは自社で全物流を担うつもり」という場合は、慎重な判断が必要と言えるでしょう。
委託したあとも、運営内容をことこまかに確認できる委託先を選ぶことが大切です。
【責任の所在】トラブルが起こったときの対応があいまいになる
2つ目が、責任の所在です。
物流を専門に行う企業の中には、実際のところその企業の子会社や孫会社が下請け先となっているケースもあります。万が一、トラブルが起きたときのためにも、各フローや現場の体制ごとに責任の所在を明らかにしておきましょう。業務委託のまえに、細かな方針すり合わせができる委託先を選ぶことが重要です。
物流委託サービスのシステムの主な種類

ここからは、具体的に物流委託を利用したいと思ったときに選べるよう、主な種類について紹介します。
【定額系】各物流サービスごとに価格が決まっているタイプ
物流委託を行う企業が定めたサービスごとに金額が設定されているタイプが定額系物流サービスです。
業務委託を行う範囲が決まっているので、初めての物流委託を導入するのであれば、まずは定額系を採用するとスムーズです。ただし、設定されたサービス内容の範囲での対応となるため、融通が利かないこともあります。その時は、導入後の状況を見て、次に紹介するカスタム系を検討しましょう。
【カスタム系】必要な物流サービスをカスタマイズするタイプ
カスタム系は、自社が希望する業務内容を選んで物流委託できるタイプです。自社に合った自由な物流を検討しているのであれば、カスタム系が向いています。
ただし、運用や料金が複雑化するため、導入までの準備や費用対効果などの比較・検討には、少し手間も時間もかかります。導入する際は、しっかりと計画を立て、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
業務委託サービスの導入方法

最後に、業務委託サービスの導入方法について、簡単な流れとポイントを紹介します。
STEP1:自社の物流における課題を整理
物流を業務委託する場合、まずは自社の物流における課題を整理します。物流の課題が把握できていなければ、外部に業務を依頼しても 自社の物流サービス品質が最大限に改善されないということもありえます。しかし、現状の課題確認や委託の範囲などを含め、事前に細かなすりあわせができる委託先であれば安心です。
必ず、どの課題の解決を優先するかを整理してから、アウトソーシングする範囲を決めるようにしましょう。
STEP2:物流委託をする業者を選定
自社の物流における課題を整理すると、業務の中で切り離したい業務が分かってくると思います。その把握できた外部へ委託したい作業内容をもとに、自社の方針や経営戦略に沿った運用に協力してくれる企業を選びましょう。
- 委託企業選びにおける注目ポイント一例
-
- 委託したい業務内容と委託業者の強みが一致しているか
- トラブルを防ぐ対策や施策を講じているか
- ノウハウやシステム構築に優れているか
実際に倉庫や作業現場を見てみることも大事です。
STEP3:見積り・提案書の作成を依頼
いくつかの企業に絞り込んだら、どのような物流サービスを期待できるのか、またその費用はいくらなのかを比較するため、提案書や見積書を依頼します。提案書や見積書では、以下のような情報に注目して見ましょう。
- 提案書や見積書における注目ポイント一例
-
- 物流の悩みを解決する提案や改善提案をしてくれるか
- 含まれる作業内容・含まれない作業内容の確認
- 費用は妥当か
- 梱包資材費は無料か有料か
STEP4:契約・委託(導入)
各企業の提案や見積りを比較し、自社の方針や経営戦略に即した運用ができるところを決めたら、契約を交わします。
契約や導入の際には、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
- 業務委託契約の際の注目ポイント一例
-
- 委託業務の内容
- 業務委託費用
- 業務委託期間や中途解約時の費用など
- 万が一のトラブルの際の損害賠償の請求
まとめ:自社の現状や展望に合った物流委託で物流フローを構築しよう
物流委託を利用する企業は多く、物流における幅広い業務を委託でき、3PLよりも広い範囲をカバーするフルフィルメントサービスも増えています。ただ、物流委託にはメリットが多い一方で、委託先選びを慎重に行わなければデメリットも生まれます。 そのため、自社の課題を洗い出し、現状や将来の展望に合った計画を立て、物流委託を活用してリソース軽減や業務効率化を図って、売り上げにつながる物流フローを構築しましょう。
千趣会では、「ベルメゾン」など自社ブランドの通販事業で培ったノウハウをもとに、お客様の事業に寄り添った課題解決のご提案が可能です。物流委託を 慎重に検討したいという ご担当者様は、ぜひご相談ください。